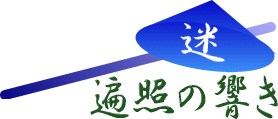
 H15/4/25up
H15/4/25upHOME > 遍路・巡礼 > 四国遍路第一章「目次」 > 高知-9 托 鉢
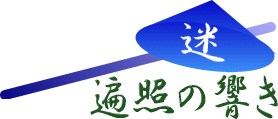
 H15/4/25up
H15/4/25up
たいていの参拝客は、無視して目をそらし、その場を避けるように離れて通り過ぎ、あの姿カッコウを見れば。だれも修行している人だとは絶対に思わず、単なる小汚いコジキとして見ると思います。
はい、その不愉快な気持ち、どんな思いで、その人達を見てるか、よぉ~わかります・・が、実は私も尺八吹いて托鉢した事があるんです・・寺に断りもなく、門前で黙ってですが。
なんせ「境内での托鉢を禁じます 四国霊場会」という紙が貼ってますからなぁ。
そんな紙を見ながら、正直に寺へ了解を貰いに行ったら、ドヤされるかもしれん・・と思いますわなぁ・・気の弱い人間としては・・・。
ホンマは寺から断られた場合の対処も、大切な修行なのでしょうが、すんまへん、コンジョウと修行が足りないもんで、もおちっと修行したら正直に了解を貰いに行きます。

三巡目の雲辺寺で初めての尺八を吹いて托鉢をやりましたが、この時は久しぶりに足が震えました。
本堂等では足の震えも無くなり、周囲のザワつきも気にならんようになったのですがねぇ。
今までのような単に寺で尺八を吹くのと違って、比較できんくらいの緊張を強いられ、もんのすごい修行になりました。
例えるならば、今までの本堂等でしていた尺八参拝は道場内での竹刀練習であり、托鉢の尺八は真剣を振りかざして勝負をする、触れば血潮が吹き出るほどの差がありました。
自分の尺八を第三者がどのように聞き、顔をさらして真正面から判定を下され、その評価が喜捨という形で表れるので、ストリーミュージシャンと同じですわなぁ。
演奏会のように義理の拍手・賞賛でなく、聞いたまんまの正直な評価がわかります。
笠を投げ銭の受け皿として置き、それでも30分ほどで1300円ほど笠に入ってました。
朝早かったので、それほど沢山の人が来てないし、また初めての托鉢で興奮しちまったもんだから、トットと早仕舞してその場を離れたました。
その時、すれちがった団体のオバチャンから「あらぁ~・・帰りに入れてあげようと思ってたのに、もう居ないわぁ」という声が聞こえました。
これに味しめて、大宝寺門前の大きな杉の木の下でやった時は、人が少なく全然入らず、青龍寺の遍路道でもやってみましたが、これも車遍路が多く、わざわざ停めてまで入れてくれる人はいませんでした。
金剛頂寺の門前でやった時は、ジャラジャラと小銭が数百円入りました。
最御崎寺でもやりましたが、その頃には私の托鉢のやり方を聞いて、チエを付けてくれる人が居りましてなぁ。
今までのように地面に笠を置いとるだけでは、単に尺八吹いてるだけと思われてしまい、托鉢してるとまで思われる可能性は少ない。
そこで地面に綺麗な手拭いを畳んで置き、その上に100円ショップで買ってきたお椀を置いて、横にお経の本と数珠を置いておけば、あぁぁ・・この人は、尺八吹いて托鉢してるんだなぁ・・・とわかる。
うんうん・・さよか・・最御崎寺へ行ってみると、若いアンチャンが階段前の修行大師像の前で托鉢しとります。
アチャアァァ~・・ワシがやろうと狙っとった場所なんじゃけどなぁ・・・
ちゃんと立って経を詠んでおり、早朝で、まだだれも入れてくれてない茶碗に小銭を入れました。
遍路は相身互いじゃからのおぅ・・・
別の遠く離れた門近くの脇道で、教えられた通りに茶碗等を置き、杖は今までは近くに置いていたのを、抱えるように腕の中へ入れて笠は被ったまま托鉢を始めました。
30分ほど托鉢しとると、さっきのアンチャンが来て立ち止まったのがわかります。
さっき私が入れたのを覚えていたのか、小銭を入れて行きます・・うん・・相身互いじゃなぁ・・・
父の友達に尺八吹いてヒマさえ有れば托鉢してた人が居たらしく、その人に「儲かるか?」と聞くと「金じゃないよ」と言われたそうです。
私も、その人が「金じゃないよ」と行った気持ちが、なんとなくわかる気がして、こればっかしは、やった人でないとわからんと思う。
うまく言えまへんが・・・なんちゅうか・・・尺八を聞いてどのような評価・行動を起こすか、どのような喜捨のしかたをするか等の行動等を見てると、これが言っちゃあ悪いけど面白いんです。
喜捨の仕方で、あぁぁ・・この人は信心で喜捨してくれてるんだ・・とか・・
この人は、ついでだから入れとこ・・と喜捨したんだとか・・
なんとなく、わかるんですなぁ。
托鉢は、相手に対して布施心を起こさせるため・・・と聞いておりますが、ワタシャアそんな大それた事は、コレッポッチも思ってまへん。
ほんまにスンマヘン・・・なんせニセモンなもんで・・・。
なお、この托鉢の思いは、私だけが、そのように思ってるので、そこんとこは誤解無きよう。
暗符しとる曲を全部吹くと約30分かかり、一曲吹き終わる毎に、ゆっくりそのまま10呼吸して、その間に少し肩や手の指を動かして凝りをほぐします。
だいたい連続して2回転吹くと1時間余り・・・その頃になると尺八持っている腕が痛くなるので、ボチボチそこらで止めてます。
ある日「道の駅」で会ったバサマ遍路の笠が、普通の安物の笠と違うので、坊さんか?と聞くと、僧籍を持っており荷物の中に僧衣が入ってるので托鉢する時はそれに着替えてるそおです。
寺の門前での托鉢は、職業遍路も食べなければいけないので、その人達に場を譲っており、自分は門前には立たず家を巡って托鉢している。
家を巡る托鉢は、寺の門前に立つ時よりも勇気がいり、家の中からは鬼が出て来るか、仏が出てくるか戸を開けるまでわからないと言います。
私のような、いつでも遍路や托鉢を止める事ができ、気楽な逃げ場の有る者とは違い、やっぱり実際に厳しい修行して托鉢する人の言葉は、もんのすごく重いですねぇ。
大日寺の門前で、黙って托鉢しょうと思いましたが、あららあぁぁ~・・先客がおります。
たぶん職業遍路さんでしょう、しっかりした声で読経しながら立っており、右手に杖をしっかり握り、左手に数珠を巻き付けて鉢を持って微動だにしません。
うぅぅむぅ・・だいぶ年季が入ってまんなぁ・・・人が居ようが居まいが、はっきりした声で読経を続けており気迫が滲み出た不動の立姿で托鉢しとる人は、今まで見た事なく、いかにも風雪に耐えて永年遍路しとる感じがしました。
はっ・・私の托鉢ですか?・・・はい、先客が居る時は、その場ではやりません。
四国遍路で托鉢する人がどのような目で見られているか、よぉ~くわかっています。
それを耐え忍んで目線をグウッ~と低い所に置き、人様から施しを受ける最低限の立場まで追い込むと、見えない何かが見え、何かがわかるような気がします。
「遍路たる者、1日最低3軒の家を訪ね托鉢せよ」と言う言葉は、それを教えてくれてるような気がします
また、家を巡っての托鉢は、その家での加持祈祷を頼まれる事も有ると聞いてますので、それなりの作法は知ってないとアカンでしょう。
芸事で何かを掴もうとする人は、托鉢をしてみれば何かがわかり、少なくとも舞台度胸は大いに付きます・・ただし、もんのすごく勇気が要りまっせぇ。(^O^)
大日寺から国分寺までは、のどかな田園風景の小道を歩きます。
恥ずかしながら「YouTube」に尺八曲「手向」を載せており、聞いて頂ければ泣いて喜びます。
当「遍照の響き」ホームページに掲載されている写真が![]() で販売されています。
で販売されています。
以下、広告です。
|
|
|
|